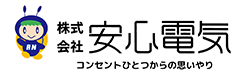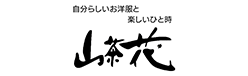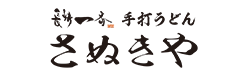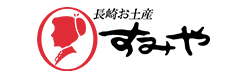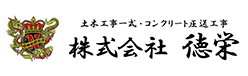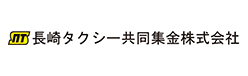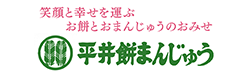-

-

諏訪町「龍踊」
すわのまち じゃおどり中島川沿いに位置する諏訪町。
その名は、かつて諏訪神社が祀られていた場所の門前にあったことに由来すると言われています。
龍踊の歴史は139年。諏訪町の龍踊には、諏訪神社の使いが「白蛇」であることにちなんだ「白龍」に加え、「青龍」に「子龍」「孫龍」も登場。スピード感あふれる「玉追い」、玉を探す「ずぐら」、走り疲れた龍の「眠り」、そして子どもたちが演じる「子龍」。次々に繰り出される多彩な演出で観客を魅了します。
諏訪町の龍踊の見せ場のひとつは、龍の動きを止めずに玉使いと龍方が一斉に入れ替わる大技「棒交代」諏訪町のお家芸です。
大きく、高く、美しく、縦横無尽に天をかける、諏訪町139年の伝統の龍踊です。

-

新大工町「詩舞・曳壇尻」
しんだいくまち しぶ・ひきだんじり江戸時代に大工が多く暮らしていたことから、この名がついたと伝えられている新大工町。
奉納のひとつは、120年以上の伝統を守り続けている唯一の「曳壇尻」
壇尻は奈良の春日大社をイメージした総ヒノキ造り。前後、斜め、右回りと、根曳衆が力を合わせて曳き回します。
最大の見せ場は5回転半の壇尻回し。
もうひとつの奉納は、10人の舞人による「詩舞」。
演目は、国土の美しさ、国の尊さ、あらゆる人々の繁栄を祝う「祝賀の詞」、坂本龍馬の維新黎明期を駆け抜けた生きざまを表した「坂本龍馬を思う」など3演目。
きらびやかな「詩舞」と勇壮な「曳壇尻」。
町の新しい伝統を紡ぐ舞人と根曳たちが、諏訪の舞台を彩ります。

-

榎津町「川船」
えのきづまち かわふね筑後の榎津産の家具を移入して販売する商人が多く住んでいたことに由来すると言われる「榎津町」
中島川が近いことにちなみ、約175年前から奉納している伝統の「川船」は16人の根曳衆が重さ3トンの船を縦横無尽に曳き回し、激流に逆らいながら荒々しく進むさまを表現しています。
江戸時代から続く伝統を重んじ、あえて演技に変化を加えない、こだわりの「時計回りでの船廻し」
一番の見せ場は直進から回転に切り替わる瞬間。勢いを殺さず、流れのままに回転に入るスピード感が持ち味です。
見どころの一つは、網打ち。大きく、美しく、網を広げて、目指すは一網打尽。
175年の歴史を誇る川船が、諏訪の舞台で躍動します。

-

西古川町「櫓太鼓・本踊」
にしふるかわまち やぐらだいこ・ほんおどり江戸中期から明治後期まで、九州で唯一、大相撲の本場所が行われていた長崎。
その興行を取り仕切っていた西古川町が奉納するのは、櫓太鼓と本踊。
相撲ゆかりの演し物を奉納しておよそ350年。
ウクライナ出身で長崎鶴洋高校相撲部のエゴール・チュグンさんが弓取り方を務めます。
西古川町のもう一つの演し物が、本踊「諏訪舞清流晒女(すわにまうきよきながれのさらしめ)」
花柳芳郁女師匠らの指導のもと、3歳から高校2年生までの踊子たちが古き良き中島川の情景を可憐に表現します。2メートルを超える「さらし」を使った演技が見所です。
相撲ゆかりの西古川町。目指すのは、湧かせるだけでなく、ひきこみ、心清める奉納です。

-

賑町「大漁万祝恵美須船」
にぎわいまち たいりょうまいわいえびすぶね「ホーエイ・エイエイヤー」
大漁を願うかけ声をあげながら、子供と大人が、勇壮な船回しを披露する賑町の「大漁万祝恵美須船」
かつて中島川沿いには魚市場があり、豊漁の神・恵美須様にちなみ、賑町では39年前から恵美須船を奉納し、今回で6回目。始まりは恵美須様が活きのいい鯛を釣りあげます。
大漁を祝う2隻の子舟と、親船の恵美須船。3隻の親子船が海の漁を繰り広げます。
獲物を一網打尽にする「網方」、船を導く舟采・そして囃子。59人の子供たちが海の漁を表現します。
恵美須船の船回しの合図を司る「大太鼓」。笛を使わず、太鼓一つで船全体を導くのが賑町の伝統です。
鮮魚店の息子が釣り上げる、大漁の象徴。父の背中を追う娘が叩く、船の鼓動。
親子の思い、町の歴史を乗せた恵美須船が、諏訪の舞台に、万雷の喝采を呼び込みます。